秋の気配が濃くなってきた先日、東京都葛飾区にある宝蔵院へ、彼岸花の撮影に行ってきました。私の旅は、いつだってドラマの幕開けから始まるのがお決まりでして、今回も例外ではありませんでした。
まず、JR松戸駅での乗り換え。快速から各停への乗り換え時間がわずか2分。「いける!いけるぞ!」と、アスリートのような気合でホームを駆け上がったものの、一瞬、頭の中が真っ白になってホームを失念。目の前で無情にも扉が「スッ…」と閉まる音を聞きました。いや、私にとっては「ザンッ!」という断罪の音でしたね。たかが電車を一本逃しただけなのに、一気にテンションはだだ下がりです。
気を取り直して、目的地のJR亀有駅に到着。ここからはバス移動です。乗換案内では「新小53」系統と出ていましたが、バス停に停まっていたのは「新小58」系統。途中バス停に「奥戸二丁目」と書いてあるのを確認し、「まあ、きっと通るだろう」という、根拠のない論理的思考で乗り込みました。結果、何の問題もなく「奥戸二丁目」バス停で下車でき、私の直感分析は今回も勝利を収めたわけですが、ここからが本番でした。

Googleナビの案内通りに歩いて到着したのが、なんとも年季の入った、サビて固く閉じられた鉄の門。どう見ても「入口」というよりは「関係者以外立ち入り禁止の裏口」です。「え、ここ…行き止まり?」と一瞬途方に暮れましたが、歴史あるお寺に迷宮のような裏口があるはずがない。

おかしいな、と首を傾げながら壁に沿って歩き出すと、角を曲がった先に、ようやくひっそりとした本来の入口を見つけました。いやはや、彼岸花が咲くお寺にたどり着くまでに、すでにミステリー小説を一冊読み終えた気分です。

ようやく境内に足を踏み入れると、先ほどの道中のドタバタが嘘のような、静かで厳かな空気が私を包み込みました。
宝蔵院は、1395年創建という歴史を持つ真言宗の古刹です。その落ち着いた空間に、秋の使者である彼岸花が咲き乱れていました。毎年およそ1000株もの花が咲くそうで、境内は赤が中心ですが、よく見ると白や黄色の花も混じり、あたり一面が鮮やかな色彩の絨毯と化しています。その光景を目にした瞬間、一気に気分が上昇し、松戸駅での失態や、サビた門に惑わされたことなど、どうでもよくなりました。やはり自然の美しさは、人間のちっぽけな悩みなど一瞬で吹き飛ばしてくれます。

特に印象的だったのは、本堂前やお地蔵さまの周りに立ち並ぶ、数多くの石仏群です。赤い頭巾と前掛けをつけたお地蔵さまと、長い歴史を感じさせる石仏の群れは、ただでさえ厳かな雰囲気ですが、その足元を真っ赤な彼岸花が埋め尽くしている姿は、まさに息をのむ絶景でした。
この石仏群は、かつて無縁仏となったり、明治時代の廃仏毀釈で土の中に埋められたりしたものを、後に掘り起こしてここに祀ったのだそうです。幾多の苦難を乗り越えて静かに佇む石仏と、情熱的な赤で一斉に咲き誇る曼珠沙華。静と動、歴史と生命力が調和するこの場所でしか体験できない感動でした。

ちなみに、本堂前には、夏の花であるサルスベリがまだ名残惜しそうに咲いていました。夏の終わりと秋の始まりが同居する、なんとも贅沢な光景です。

白や黄色の彼岸花が咲き始めていました。今年も昨年同様、開花はやや遅れているようで、まだ蕾も残っています。それでも赤・白・黄色と彩り豊かに咲き誇り、ちょうど見頃の美しさを楽しむことができました。

背後にそびえる薬師堂を背景に、彼岸花がひときわ映えていました。堂内には「式部薬師」と呼ばれる木造薬師如来立像が安置されています。気温が下がってきて蚊の動きが活発になっているため、訪れる際は虫除け対策もお忘れなく。

亀有駅からは京成タウンバスの新小岩行きに乗り、「奥戸二丁目」バス停で下車すると宝蔵院はすぐ目の前です。JR小岩駅からは徒歩約20分でアクセス可能。バス路線の案内は新小53が一般的ですが、新小58でも利用できるため、便の良い方を選んで訪れるのがおすすめです。

宝蔵院で感じたのは、歴史の重みと、それを彩る自然の美しさの調和です。
思わぬ乗り換えミスや、サビた鉄の門という「試練」を乗り越えてたどり着いたからこそ、一層、この静かな空間と、目の前に広がる曼珠沙華の群生が、より感動的に映ったのかもしれません。
都心から比較的アクセスが良く、気軽に秋の散歩や撮影を楽しめる貴重なスポットです。今年の秋は、ぜひ皆様も宝蔵院の彼岸花を訪れて、情熱的な赤、清楚な白、そして希望の黄色が織りなす彩り豊かな曼珠沙華と、歴史あるお寺の深みのある風情を味わってみてはいかがでしょうか。
私も、次回は迷わず正面の門から入り、さらに深く、宝蔵院の魅力を探求したいと思っています。








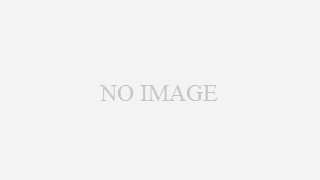














コメント