毎年恒例、秋の風物詩といえば、茨城県常総市の弘経寺(ぐぎょうじ)の彼岸花ですよね。
私にとって、この情熱的な赤をレンズに収めることは、秋の始まりを告げる重要な儀式の一つです。

ただ、ここ数年の彼岸花さんたち、どうも「私ってそんなに簡単に見頃を迎えないのよ?」という態度が過ぎるというか、お彼岸(秋分の日)の近くには、なかなか本気を出してくれないんです。
もう、彼岸花さんったら、ツンデレが過ぎますよ!花にまで振り回される私……。これもまた人生でしょうか。
今年も例に漏れず、お彼岸を華麗にスルー。
今年の気候が昨年と同じく「秋らしからぬ夏の延長」であると冷静に分析し、「ならば見頃は今年も9月下旬で間違いない」と論理的に推測いたしました。
そして、まさにその予測通り、境内一帯が深紅に染まり始めた頃合いを見計らい、カメラを抱えて飛び出してきました。

弘経寺の彼岸花は、なんと約5万株という、もはや「株主総会」級の圧倒的なスケールなんです。
これが一斉に咲き揃うと、境内に敷かれた「赤い絨毯」は、まるで大地が真っ赤なドレスをまとったかのような壮観さ。
この物理的な量が、視覚に訴えかける力は絶大です。

しかし、撮影当日の空は、期待していた「朝の光」を完全にシャットアウトした曇り空。
オマケに気温は高く、空気はちっとも秋らしくない、夏の延長戦の暑い朝です。
撮影者としては「光がない」というハンデを負いましたが、彼岸花たちにとって、この曇天はかえって好都合だったのかもしれません。
熱を持った空気の中、地面を真っ赤に染め上げる情熱的な赤の絨毯は、曇り空の下でもその存在感を誇示しており、『光がなくても、私たちは美しい』と主張しているようでした。
私が訪問した日は、まさに「見頃の真っ最中」。
満開宣言まではもう一息といったところでしたが、その分、花の色が非常に鮮やかで、特に曇天の均一な光は、赤の色飽和を防ぎ、花びらの質感を際立たせてくれました。
結果として、重厚感のある深紅を捉えることができたのは、予想外の収穫です。
平日の朝にもかかわらず、熱心なカメラマンさんや、散策を楽しむ方々で賑わっていました。
やはり、良いものは皆知っている。「光がなくても、テクニックで勝負!」という写真家の闘志は、ここ弘経寺でも不変の真理だと再認識です。

境内の見どころの一つ、防火水槽の辺りは、満開になるとまさに圧巻の景色になるのですが、この日はまだ「準備運動中」といった感じでした。
これから訪れる方は、最新の開花状況をチェックしつつ、「防火水槽前、満を持して」というタイミングを狙うのが、最高の景色を捉えるための勝利への近道でしょう。

弘経寺の魅力は、彼岸花が描く色彩の暴力だけではありません。
応永21年(1414年)創建の浄土宗の古刹であり、あの徳川家康公の孫、千姫ゆかりのお寺として、歴史好きの心も同時に満たしてくれます。境内を歩くと、千姫のお墓があったり、さりげなく徳川家の葵の御紋が鎮座していたり。
江戸時代の建築様式を残す本堂や、凛とした杉木立、苔むした石畳など、「歴史」と「自然」が完璧なハーモニーを奏でているからこそ、彼岸花の赤がより一層映えるのだと、私は分析の結果、強く主張します。

そして、遊び心も忘れていないのが素敵。手水舎(ちょうずや)には、粋にも深紅の彼岸花がそっと浮かべられていました。まるで「ようこそ」と言ってくれているようで、私のテンションもMAXに達しましたね。

しかも、赤一色で終わらないのが、このお寺の奥ゆかしいところ。情熱の赤をメインに、時折顔を出す純粋な白や、陽気な黄色の品種たちを見つけると、「あ、ここにも個性派が!」と、まるで宝探しのような楽しさがあります。花好きの私としては、この色の多様性こそが、多くの訪問者を惹きつける「たまらない光景」だと論理的に断言せざるを得ません。

黄色彼岸花、ショウキズイセンは見頃を過ぎていました。

参道の桜の木の下にも彼岸花が咲いていて、最後まで気の抜けない、見応えのある撮影地でしたよ。
今回、改めて弘経寺を訪れて感じたのは、「歴史が持つ重厚感」と「彼岸花の命の軽やかさ」という、対極の美しさが混在する場所のパワーです。
曇天と暑さの中、燃えるような赤い絨毯をカメラに収めながらも、千姫の歴史に思いを馳せる…こんなに情緒的でありながら、論理的な思考を巡らせたくなる場所はなかなかありません。
この場所を訪れるたびに、彼岸花が毎年少しずつ見頃のタイミングをずらしてくるその「不可解な生態」に頭を悩ませつつも、その難易度の高さが逆に私の挑戦意欲を掻き立てるのです。
今回の訪問で、気候と開花時期の相関関係の法則、そして曇天での撮影戦略をさらに深く分析できたことは、大きな収穫でした。
次はぜひ、防火水槽前の完璧な「赤い炎」と、純白の彼岸花が同時にピークを迎えるという、神がかり的な瞬間を捉えたいと思っています。
その時、この地の魅力はさらに一段階上のレベルへ到達するでしょう。
読者の皆様も、この秋、曇り空の下でも力強く咲き誇る、歴史と情熱の赤が交差する弘経寺のロジカルな美しさを体験しに訪れてみてはいかがでしょうか。









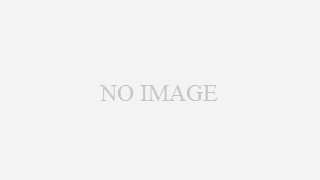














コメント